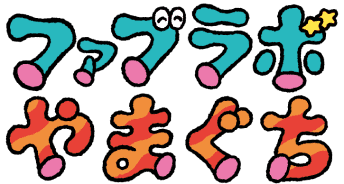制作事例_vol.20|染織作家|垂井 美穂さん

自然の色や質感をアーカイブすることをテーマに染、 織、縫などの技法を都度組み合わせて1点もののテキスタイルや装身具を制作。山口に住み始めてから周りの自然の豊かさに触れ、身の回りの植物を使った染めの表現を模索中。
ファブラボを知ったきっかけは?
私は2021年から3年間、山口市で地域おこし協力隊の活動をしていました。
その協力団体だったVIVISTOP山口の方からファブラボを教えていただいたのがきっかけです。
VIVISTOP山口は道場門前商店街に拠点があって、クラフトツールやデジタル機器を使い「アイディアを形にする活動」を進める団体です。
その点ではファブラボとも通じる部分が多くあると思います。
普段はどんなことをされていますか?
自分で染色した布やアンティークの糸、古布などを使った作品を制作しています。
それと並行して、以前から携わっているグラフィックデザインの仕事も続けています。
ファブラボで作ったものを教えてください
主に2つあります。
1つ目は(自身の)ブランドロゴを箔押しで作りました。
ファブラボで行われた「シルエットカッティングマシン体験会」のときに作りました。
この機材は裁断だけでなく箔押しもできると聞き、ちょうどブランドロゴを作りたいと考えていたので、本当に絶好の機会でした。
2つ目は、レーザーカッターを使って木製道具を作りました。
作品制作のとき、布や紐などを巻く板を何点か作りました。
もちろんこういった既製品は販売されていますが、私としては木製の方が手に馴染んで使いやすく、作風にもマッチすると感じていたので自作することにしました。使用する道具が定まったことで、細かい道具の使い分けという手間が減りましたし、増え続けた道具の収納問題も解決できました。
今は自作道具を試作品として使っていますが、想像以上に手に馴染み、作品制作も捗るのでサイズ違いのものを複数作ろうと思っています。
自作した中でも特に良かったのは簡易織り機用の板杼(いたひ)という道具です。
板杼(いたひ)は、機織り機で経糸(たていと)の間に緯糸(よこいと)を通すための道具のことです。
既製品を使っていましたが、やはり自分の手のサイズに合わないことが多く苦労していました。自作したことで、本当にしっくりくる道具を手に入れられたと感じています。
この作品の中で、工夫したポイントは?
レーザーカッターで一度切り出した後の細かな調整ですね。
私にとって道具類は、数値で測れない部分が多いことを実感しました。
何よりも実際に使って、手に触れた感覚が大切なので納得いくまで微調整を繰り返しました。
でも、その甲斐あって最高の相棒を手に入れることができました。

あえて言うなら「ここ、ちょっと困った…」と思ったことは?
あえて言うなら…シルエットカッティングマシンかな?
シンプルなロゴデザインなのに出来上がりは微妙にイメージと違っていて、線と面の設定を何度もやり直しました。
苦労した分だけカッティングマシンと仲良くなれたので、逆に創作意欲が掻き立てられたのでよかったです(笑)
完成したとき、どんな気持ちでしたか?
何よりも「オリジナルを手に入れられた喜び」を感じました。
既製ではなく唯一無二、自分の手に合う、感性にマッチするものが手の中にある。それって本当に嬉しいですよ。オリジナルを手に入れる喜びは格別だと思います。
私は、手で触れるモノは見た目の印象と、実際触れたときの印象が違うことが多いと感じています。
既製品の場合は手にしたときの違和感を解消しにくい。でも、自作の場合は想像通りになるまで何度でも修正することができます。
確かに調整の過程は大変だけど、それだけ完成したときの感動は大きいので自作する価値は計り知れません。
スタッフとのやりとりで印象的だったことは?
「引き出しが多い」と感じたことですね。
ファブラボには、実践の結果生まれた解決策がたくさんあるということです。
私の疑問1つに対して複数パターンの提案が瞬時に出てくることには驚きました。
スタッフの方自身が既に試行錯誤を経ている証拠だと感じましたし、このことがスタッフの皆さんへの大きな信頼に繋がったと思います。
例えば私の場合、レーザーカッターの使用経験はあっても、マシンの設定は作品によって変わるので詳細はその場で調整しなければなりません。
ファブラボでは素材に合わせて、柔軟に複数の設定を提案してくださるので使い方のバリエーションが増えたと思います。
ファブラボで「今後やってみたいこと」はありますか?
オリジナル作品を収納するオリジナルの箱を作りたいですね。
個人作家さんあるあるだと思うのですが、1点ものを収納するとき作品にジャストフィットの箱が欲しくなります。
私は1点ものだからこそ、それを収納する箱も1点ものであるべきだと考えています。その箱が完成したら、こだわりの彫刻も入れるなどとことんオリジナルにこだわっていきたいと思っています。
「こんなことができたらいいな」と思うサービスはありますか?
カッティングシートを自作できたり、シルクスリーンが使えたりすると嬉しいですね。
今後は小さな作品でもよいので、色のバリエーションを増やして作ってみたいと考えています。
だから、使える機材が増えると作品制作のアイディアの幅も広がるかなと思います。

ファブラボに来る前に不安だったことはありますか?
機械の操作手順と作業時間など、多少の不安はありました。
でも、実際やってみるとスタッフの方にフォローしていただき、特に迷うことなく時間内に終えることができたので思い切って来てよかったと感じています。
もし時間や費用に制限がなければ、ファブラボでどんなものを作ってみたいですか?
私は3Dプリンタを使ったことがないので、次回は挑戦してみたいですね。
オリジナル道具の魅力にハマってしまったので、その可能性を更に広げていきたいと思います。
ファブラボの魅力はどこにあると思いますか?
何よりもこの自由な環境です。
豊富な機材が自由に使えること、スタッフの丁寧なフォローが受けられることは大きな魅力だと思います。
素材の特性を見極めた専門的アドバイス、スタッフも制作者と一緒にものづくりする姿勢、ものづくりを志す人にとって本当に心強いと思います。
これから利用してみたいと思っている人に、ひとことお願いします!
アイディアだけ持って行けば大丈夫、あとはなんとかなります(笑)
一歩踏み出せば、迷いで止まっていた時間が動き出す場所、それがファブラボです。
まずはその一歩、そこから世界が変わると信じて行ってみてください。

染色「奥の細道」
地域協力隊の任期を終え、新たに作家活動をスタートした垂井さん。
その拠点に選んだのは潮の香りを間近に感じる閑静な住宅街。趣き深い佇まいの中に緩やかな時間を携えた工房兼アトリエにお邪魔させていただきました。
「エアコンが無いから暑いと思いますよ」と聞かされ若干身構えましたが、時折室内を抜けていく風が心地よく、むしろ涼しいぐらい。
「この海風のおかげで山口市内よりも快適に暮らせます」という言葉にも納得です。
1階は工房、広い土間に大きな作業台、窓際にミシン、奥には染め場が設えてあります。
2階はアトリエ、壁や扉は取り払われ、明るく開放的なスペースを確保。
入居当初は掃除と修繕に追われる日々で大変だったと聞きましたが、それを微塵も感じさせない整った空間が広がっています。
まずは2階のアトリエでインタビュー。
撮影時、「Tip Tie(ティップタイ)」というイベントに関わっておられるということで、まずはそこからお話を伺いました。
「Tip Tie」は2024年TipTie実行委員会(下関市地域おこし協力隊・まちづくりに取り組む市民有志ら)により始まった試みで、下関市内の店舗をアートギャラリーに見立て「日常」を感じながら「地域の魅力」に触れて、まち全体を愉しむ「回遊型イベント」に今年も垂井さんは参加されていました。
その後、1階の工房へと移動。
ここで印象的だったのは、壁に立てかけられた大きくて真っ白な生地ロール、その横に高く積み上げられた生地の山でした。
グラフィックデザイナーであり、染織作家でもある垂井さん。
グラフィックの仕事では、計算された色の組み合わせを楽しいと感じる反面、直感的な色表現をしたいという思いに駆られることも多かったそうです。
染色では、直感的に色を選び、思いのまま染めあげることができる。そのダイレクトな表現方法こそが染色に魅せられたきっかけだと話しておられました。
垂井さんは「色を使ったものづくり」実現のため、染色作家への第一歩として遠くスウェーデンへと旅立ちます。現地の学校で染色について学ぶ傍ら、数多くの書籍や資料を読み、足しげく美術館へ通うなどし、独自の表現を探究する日々を過ごされました。
「同じ色に染めるのが最も難しい」
染色は植物の採取時期(季節)や採取した条件など植物の状態が色に影響するそうです。
実際、ノートには染色のための細かな情報がびっしりと書き込まれています。
使用した材料はもちろん、制作時の天候、気温、湿度などの数値データまで、丁寧に綿密に書き記されています。また、各ページには染色したサンプル布がたくさん貼り付けてあり、とても分かりやすく工夫されていました。ページをめくりながら「実験をしている気分です」という垂井さん。
確かにどのペーシにも試行錯誤の爪跡、工夫の輝きが詰まっています。繰り返し観察し記録を重ねていく過程をお聞きしていると、新薬の研究開発のようで工房は理科実験室のように感じてきました。
今後の活動についてお尋ねすると「何よりもこのアトリエが持っている懐かしい空気感や、くつろげる雰囲気を大切にしていきたい」更に「もっとたくさんの方と一緒に活用できる開かれた場所にしていきたい」と話されました。
この地域には作家さんや、個人でものづくりされる方が増えているそうで、その人たちとつながりながら自身の活動を広げていきたいと意欲的に語っておられました。
染色とは、同じに見えて違うもの、唯一無二の表現、同じものは生まれないし同じものには出会えない世界。厳しくて切ない、それでいて新たな出会いと驚きに満ちた世界。それはまさに一期一会、どこか茶道や俳句の世界と通じるものを感じてしまいました。
染色の世界を歩く垂井さんの旅はどのあたりなのでしょう。その歩みのあとに咲く数々の色を想像すると胸が高鳴ります。今後も「色彩の求道者」垂井さんの活動を追っていきたいと思います。
垂井さん、お忙しい中ありがとうございました。
MIHO TARUI
Webサイト:https://www.mihotarui.com/
Instagram:@rururu_miho