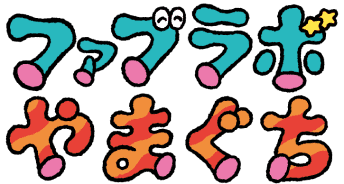制作事例_vol.18|一般社団法人 スポーツタイムマシン|代表理事 廣田 祐也さん

「スポーツタイムマシン」は、スクリーンに映し出される昔の記録と実際に「かけっこ」できる装置です。
自分の記録だけではなく、家族や友達、動物の記録に挑戦することができ、毎回記録は記憶され更新されてゆきます。
この装置でスポーツを通して、過去・現在・未来を横断した継続的な身体コミュニケーションを提供します。このタイムマシンをみんなで作り、長い期間大切に運営していくプロジェクトです。
ファブラボで作ったものを教えてください
今回はMDFとアクリルを素材にし、レーザーカッターでオリジナルロゴを彫刻した記念メダルを制作しました。
なぜその作品を作ろうと思いましたか?
韓国にあるACC(アジア文化殿堂:韓国・光州に位置する国立のアートセンター、アジア各国の文化交流と創造活動を推進する文化複合施設)でスポーツタイムマシンという作品を展示する機会を頂いたので、そのノベルティとして制作しました。
スポーツタイムマシンとは、片道25mの走路を往復し、走った速さの記録がリアルタイムに残ることにより過去の記録と競うことができるメディアアート作品です。
この作品の中で、工夫したポイントは?
特に気をつけたのは、メダルに紐を通す部分の厚さです。
デザイン上の数値と、レーザーカッターで切り出した際の数値には微妙な誤差があったので、強度とデザインの両立を考えて微調整していきました。

完成したとき、どんな気持ちでしたか?
(正直)ほっとしました。
実はこのノベルティは、韓国に出発する直前に思いついて作り始めました。そのせいで、常に時間との戦いを強いられ、完成したときは「間に合ったぁ!」という感じでした。
韓国ではノベルティを贈り合ったり、交換したりする文化が根付いているということを知り、どうしても展示会場で配りたいと思ったので、頑張りました。おかげで現地の方との関係性を深めることができ、展示を盛り上げることができたと思います。
ただ、参加者全員に配布するほどの数は準備していなかったので、限定20個で現地スタッフの方に配布をお任せしました。もっと多くの方に配れるだけ準備できればよかったという思いはあります。
スタッフとのやりとりで印象的だったことは?
色々な経験に基づいて、サイズや素材、設定など、的確にアドバイスをしていただいたので、無駄なく効率よく、満足できるデザインに仕上げることができました。
説明も丁寧で優しかったのがとても印象に残っています。
ファブラボで「今後やってみたいこと」はありますか?
僕はスポーツタイムマシンの活動をより多くの方に知っていただきたいと思っています。
この活動をもっとアピールできるようなもの、ステッカーなどの関連グッズをたくさん作ってみたいですね。
ファブラボ利用者さんの作品を参考にして、グッズの種類を増やしていければいいなと思っています。
「こんなことができたらいいな」と思うサービスはありますか?
僕は多くの利用者さんが気軽に集まり、スタッフの方を交え、短時間で親密なコミュニティが形成できる、それがファブラボの素晴らしさだと感じています。
個々の技術や知識などを交換し合えるこの環境がより発展すればいいなと思いますし、そうなればこの素敵な場所がより育っていく、輝いていくのではないかと考えます。
もし時間や費用に制限がなければ、ファブラボでどんなものを作ってみたいですか?
個人的にはカメラの周辺機器、拡張パーツなどを3Dプリンタで作りたいと思っています。
というか、作ります!
ファブラボの魅力はどこにあると思いますか?
ひとことで言えば、それは「人」だと思います。
スタッフの方はもちろん、ファブラボの利用者さんもクリエイティブでユニークなアイディアを持った方ばかりです。
ちょっと話すだけでも斬新な閃きを得たり、ものづくりに対峙する人の強い熱量を感じたりします。そういう可視化できないもの、クリエイティブな人、エネルギー、アイディアが集まる場所、それがファブラボの魅力だと思います。
これから利用してみたいと思っている人に、ひとことお願いします!
「本当にできるのか」とか、「自分には無理なのでは」と不安に思う方も多いと思います。
でも、ここなら大丈夫です。最初から助けてという気持ちでいい、気負わないで、まずはファブラボに来て、見て、やってみましょう!

初代の横顔
ファブラボの常連さんでありながら、仕事仲間の廣田さん。
ここはあえて普段どおり「廣田くん」と呼ばせていただきます。
今回のインタビューは廣田くんたっての希望で、河口さん(スポーツタイムマシン理事/ファブラボやまぐち代表)を交えての取材となりました。
お二人の出会いは2013年、YCAM(山口情報芸術センター)のスポーツタイムマシン企画の公募に、小学5年生だった廣田くんが遊びに来たことが始まりでした。
運営スタッフとして関わっていた河口さんに、当時の廣田くんの印象を尋ねてみました。
「参加者というより、新しい遊び方を模索する開発者という感じでしたね。見た目は今と全く変わりませんけど、当時から他の体験者とは明らかに熱量が違っていました」とのこと。
一方、廣田くんに尋ねてみると、「自宅がYCAMの近くだったこともあり、友達を誘って頻繁にイベントに通っていました。次第にスタッフの方とも親しくなり、友達と考えたアイディアを次々とぶつけていくのが楽しかったですね」と当時を振り返っていました。
廣田くんは河口さんを師匠、河口さんは廣田くんのことを廣田氏と呼びます。この呼び方からも、単に知人という関係性ではないことがわかります。過去のイベントを振り返るふたりの会話を聞いていると、苦労話さえ楽しそうで、一向に止まる気配がありません。その様子からも、膨大な時間を共に試行錯誤してきた親友であり、確かな信頼で結ばれた師弟なのだと感じました。
2023年、スポーツタイムマシンは10周年を機に法人化しました。その際、廣田くんは初代の代表理事に就任しました。その経緯を尋ねてみると「周りの大人からの強い後押しと、あとは成り行きで…」という、やや控えめなコメント。しかし、今の廣田くんの活躍ぶりを見れば、彼を推した方々の慧眼には感服するばかりです。
スポーツタイムマシンの今後の展開について、廣田くんに聞いてみました。
「現在はイベントへの出展など、不定期での開催に留まっていますが、理想とするのは常設展示ですね、この作品は長くやればやるほど価値が増していくので。現行の作品は走路が短いため往復して走るのですが、今後は100mを直線で走れるようしたい。記録データも100年後まで残したい。これがスポーツタイムマシンの大きな目標(スローガン)”目指せ100年・100m”です」と力強く語ってくれました。
私たちが100年後のスポーツタイムマシンの姿を確認することはできません。しかし、きっと多くの人が廣田くんの思いが詰まったバトンをリレーしてくれているはずです。
みなさん、スポーツタイムマシンのイベントを見かけたらぜひ参加してみてください。誰かの記録に挑戦するもよし、自身の記録を残し挑戦者を待つもよし、いずれにせよあなたの記録は世界中の挑戦者と繋がっていきます。
走路に立ったその瞬間から、あなたも”100年リレー”のメンバーです。さあ100年後の未来へバトンを繋ぐランナーになってみませんか。
廣田くん、河口さん、お忙しい中ありがとうございました。
スポーツタイムマシン
Webサイト:https://sportstimemacine.blogspot.com/